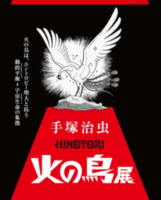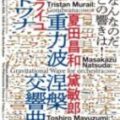東京シティビューで行われている「手塚治虫 火の鳥展」に行ってきた。
生物学者の福岡伸一氏の監修と解説で、壮大な構想の中に描かれた手塚の思想や知識が丁寧に説かれている。手塚治虫の博識とストーリーテラーとしての手腕は承知していたが、それを一つ一つ解き明かしてくれる福岡伸一にも感服した。
少年時代の手塚が描いた昆虫画の見事さは宝塚の手塚治虫記念館で見て知っていたが、福岡氏は手塚が描いた蝶の見事な写生画の横に、絵と同じ(と思われる)蝶の本物の標本を自分のコレクションから集め、絵とそっくりに並べて提示してみせる。

「手塚治虫はもう古い」という言葉をネットでしばしば目にする。会場にも若者はほとんどいなかった。でもこの稀有な才能と知識、そして彼の作品に波打つヒューマニズムを時の流れの中に追いやってはならない。福岡氏という、これまた稀有な才能に支えられて今回の展示会が実現したのはありがたい。
小学4年の頃だったと思う。本屋で雑誌『COM』と出会い、「火の鳥」と出会った。黎明編の初めの方だったと思う。いつの間にか毎月買ってもらうようになり、未来編に夢中になった。衝撃というより、この作品に世界観を作ってもらった。そうか、世界とは、宇宙とは、こういうものなんだ。





年齢を重ねて少し仏教関係の本をかじり、その流れで手塚の『ブッダ』を読んだ。ブッダの思想に『火の鳥』の世界観が重なっている。それによってブッダを超えた普遍性を得ている、と思った。
今も毎朝仏壇に手を合わせるとき、実は『火の鳥』未来編の数ページを頭に浮かべている。
追記
上記を書いたあと、古い原稿の中から「火の鳥」についての文章を見つけた。2014年に、大学図書館の広報誌から「人生に影響を受けた本について書け」みたいな依頼を受けて書いたものだ。上記と重複する部分も多いが、補足として貼り付けておく。
はじめて「なりたい」と具体的に思った職業は漫画家だった。小学校のころは石森章太郎の『マンガ家入門』をむさぼるように読み、卒業時の学校新聞には「ディズニーのようになりたい」と書いた。そのころ、「漫画の神様」手塚治虫が『COM』という雑誌を創刊した。「まんがエリートのためのまんが専門誌』と銘打たれ、漫画表現の可能性を切り拓くような作品がいくつも掲載されていた。当時の私にはよく分からない作品も多かったが、分かった気になって自分も「エリート」になったつもりでいた。そんな中で、すなおに面白いと思えたのが手塚治虫の『火の鳥』だった。
古代の日本を舞台にした第1部「黎明編」にもわくわくしたが、第2部の「未来編」はそれどころじゃなかった。未来都市と世界戦争。それ自体も大きなテーマだが、実は長い導入部にすぎない。本題はその後だ。いったん破壊された地球が再生し、新しい歴史を作っていく。一つの歴史がとだえると、再び再生がはじまる。地球も生きている。宇宙も生きている。そして生命全体は、無限に死と再生をくりかえしながら生き続ける。
時空を超越した存在である「火の鳥」が、歴史を見とどける役目を負わされた主人公に、宇宙の姿を開示する場面がある。細胞や素粒子の中に無限の小さな宇宙がつらなり、太陽系や銀河系の外側には無限の大きな宇宙がひろがっている。わずか数ページの描写だが、思春期(というのはつまり、世界と自分との関係を意識しはじめるころ)にさしかかった私に与えた印象は、強烈だった。今でも、世界とか宇宙とかという概念を考えるときには、真っ先にこの数ページが頭に浮かぶ。
リアルな世界はアトムを作れないまま『鉄腕アトム』の時代を追い越してしまったけれど、『火の鳥』未来編のはじまりまでには千年以上ある。まだまだ読みつがれる価値のある作品だと思う。
![musiquest [音楽探求]おぼえがき](https://musiquest.sakura.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2024/11/wpロゴ2色小文字.jpg)