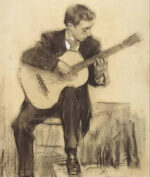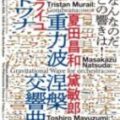問題提起:曲数、曲順、日本語タイトル
ふと〈盗賊の歌〉のメロディーが頭に浮かんで、懐かしくなった。その後も頭から離れない。
リョベート(Miguel Llobet、1878-1938)の《カタロニア民謡集》については、むかし解説を書いたことがある。大学院を出て間がない頃。音楽之友社が新書版の名曲解説集を出すというので回ってきた仕事だ。当時はこういう仕事がいくつかあって、知らない作曲家や曲にたくさん出会うことができた。今でも自分の財産になっている。この《カタロニア民謡集》もその一つ。
こんなことを書いた。
カタルーニャ民謡集
<作曲年> 1899~1918 <演奏時間> 各2~3分 <楽器> ギター
カタルーニャに生まれタルレガに師事したリョベートは、セゴビア以前の最高のギター奏者と評されているほどの名手であった。欧米各地に演奏旅行を行ない、当時最高の報酬を得る芸術家の一人であった。紳士的な人柄で知られ、スペイン内戦への悲しみのあまり病死したといわれている。ファリャが唯一のギター作品〈ドビュッシーの墓のために〉を書いたのもリョベートの為であったが、そうしたオリジナルのギター作品だけでなく、リョベートは民謡や古典から同時代の作品まで、数多くの曲を自らギター用に編曲し、演奏会で積極的に取り上げた。その中で、今日もたくさんのギター奏者たちによって愛奏されているのが、この曲である。以下に述べる十曲にまとめられた曲集が普及しているが、その他 〈聖母とその御子〉や〈エル・ポブレ・パジェス〉等の曲が知られている。
第一曲「アメリアの遺言」 死の床につく姫の歌う悲しみに満ちたアンダンテ。
第二曲「盗賊の歌」盗賊が生い立ちを振り返って歌う明るい流れのよい歌。
第三曲「糸を紡ぐ娘」 ルネサンス舞曲のような軽快な曲。
第四曲「王子」アンダンテ、八分の六拍子でシンコペーションのリズムが印象的。
第五曲「夜うぐいす」 対話風のかけ合いによるアレグレットの曲。
第六曲「哀歌」 故郷カタルーニャの運命を嘆く歌。 カザルスの愛奏した〈鳥の歌〉を思わせる悲痛な趣をもつ。
第七曲「エル・メストレ(教師の恋)」対照的な二種のフレーズが移調されつつ対話する構成。
第八曲「あとつぎのリエラ」 リズムのはっきりした三拍子の舞曲。
第九曲「商人の娘」アンダンテ、八分の六拍子の揺れるリズムが舟歌を思わせる。
第十曲「凍えた十二月(クリスマスの夜)」クリスマスを祝う楽しい曲。
以上、いずれも珠玉のような美しさを持っている。(『ON BOOKS SPECIAL 名曲ガイド・シリーズ 10 器楽曲 上』音楽之友社 1984、
なお「カタルーニャ」の表記は編集部の方針による)
YouTubeで音源など探しつつ改めてちょこっと調べてみたら、いろいろ修正や追加したい情報も出てきた。そもそもリョベートのカタロニア民謡集は何曲なのか。曲の並び(曲順)はどれが正しいのか。各曲の日本語タイトルはこれでよいのか。
それを考える前に音源をみておこう。クラシックギターでは定番のレパートリーだけあってYouTubeにもたくさん動画が上がっているが、個々の曲単体のものが多く、10曲以上まとまったものは少ない。どうせなら演奏動画の方が良いのだが、全曲が聴けて演奏もクセの少ないタンパリーニ(Giulio Tampalini、1971- )の演奏(Brilliant Classicsのギター作品全曲録音、以下全曲録音)を上げておこう。オリジナル作品も含め全41曲が収められている中、動画上の表示で1’54″から21’05″くらいまでの13曲がカタロニア民謡集。
ここでの収録曲と開始のタイミングは以下の通り。なお便宜上添えた日本語タイトルは現代ギター版(『ミゲル・リョベート ギター作品集~オリジナル作品と編曲作品~』現代ギター社 2010)による。
- Cançó de Lladre(盗賊の歌)01:54
- El Noi de la Mare(聖母の御子)03:15
- El Mestre(先生)05:00
- Lo Rossinyol(うぐいす)07:31
- L’Hereu Riera(あととりのリエラ)08:28
- El Testament d’Amelia(アメリアの遺言)09:14
- Lo Fill del Rei(王子)10:51
- La Pastoreta(羊飼いの娘)12:04
- Plany(哀歌)13:22
- La Filadora(糸を紡ぐ娘)15:00
- La Filla del Marxant(商人の娘)16:08
- La Nit de Nadal(凍った12月)18:27
- La Preço de Lleida(レリダの囚人)19:37
曲順の根拠はわからない。
曲数とエディション
上記ON BOOKSに挙げたのは10曲で、「以下に述べる十曲にまとめられた曲集が普及している」と書く一方、「その他 〈聖母とその御子〉や〈エル・ポブレ・パジェス〉等の曲が知られている」とも書いている。今挙げた「ギター作品全曲録音」は13曲で、前掲の10曲に〈聖母の御子〉〈羊飼いの娘〉〈レリダの囚人〉の3曲が追加されている。このうち〈聖母の御子〉はON BOOKSでも触れた〈聖母とその御子〉と同じだろうが、〈エル・ポブレ・パジェス〉は全曲録音に含まれていない。〈エル・ポブレ・パジェス〉はどこに行った? いや、どこから来た? ――という問題は後で見るとして、まずは「全曲録音」に含まれた13曲を全部と考えて良いのか。これについてはエディションの問題と関連するので、まずそちらを片付けよう。
(とはいえ、現時点では残念ながらエディションごとの楽譜内容の相違などに触れる余裕がないので、あくまで外形的な話にとどまることをお許し願いたい。)
UME版とギタルラ社版
ON BOOKSで「十曲にまとめられた曲集」と言ったのは、スペインのUnion Musical (UME)から出ているDiez Canciones Populares Catalanas (Ten Catalan Folksongs) のことである。Amazonなどで今でも手に入る。左が2010年版の表紙、右が1964年版(の白黒コピー)の表紙。


ネットで拾った古いUME版(表紙なし)の版権表記は1933年である。

ところで我が国ではギタルラ社から1964年に『カタロニア民謡集』が出版されている。ギタルラ社版の表紙にはベージュと青の2色があるようだが、ベージュの方が古いようだ。


どちらもUME版同様10曲で、曲順も同じ。ギタルラ社版はおそらくUME版をもとにして作られたものだろう。というわけで、UME版の曲名にギタルラ社の日本語タイトルを添えておく。
- El Testament d’Amelia(アメリアの遺言)
- Canço de Lladre(盗賊の唄)
- La Filadora(紡ぎ女)
- Lo Fill del Rei(王子)
- Lo Rossinyol(夜うぐいす)
- Plany(哀歌)
- El Mestre(教師の恋)
- L’Hereu Riera(リェラの将軍)
- La Filla del Marxant(商人の娘)
- La Nit de Nadal(聖夜(凍れる12月))
ネットではUME版で1933年の版権表示がありながら11曲含むpdfファイルも見つかった。最後にEl Noi de la Mare(聖母の御子)が追加されているのだが、このファイルについては表紙もなく、詳細は分からない。ある時点で〈聖母の御子〉を追加した11曲版が出たという可能性もあるが、だとしたら表紙のタイトルはどうなっていたのか、今なお10曲版が出版されているのはなぜか。気になるものの調べようがない。
Chanterelle版
1989年にドイツのChanterelleという出版社から『新リョベートコレクション ミゲル・リョベート ギター作品集(Nuevo Colección Llobet Miguel Llobet Guitar Works)』全5巻が出ている。編纂者はアメリカのギター奏者パーセル(Ronald Purcell, 1932-2011)。カリフォルニア州立大学の先生で国際ギター研究アーカイヴという組織を作っていた学究肌の演奏家。UMEはじめ版権を持つ出版社から承諾を得て出版できた、という謝辞が付いている。


第2巻が16 Folksong Settingsと題されており、最初の13曲がカタロニア民謡(13 Canciones Catalanas)、そこにレオン地方の民謡(Leonesa)1曲およびアルゼンチン民謡2曲(2 Estilos Populares Argentines)が追加されている。カタロニアの13曲は上記全曲録音と曲は同じだが順序は違う。現代ギター版の日本語タイトルと、Chanterelle版各曲に添えられた作曲年も記しておく。
- Plany(哀歌)(1899)
- La Filla del Marxant(商人の娘)(1899)
- El Testament d’Amelia(アメリアの遺言)(1900)
- Canço de Lladre(盗賊の歌)(c.1900)
- Lo Rossinyol(うぐいす)(1900)
- Lo Fill del Rei(王子)(1900)
- L’Hereu Riera(あととりのリエラ)(1900)
- El Mestre(先生)(1910)
- La Nit de Nadal(凍った12月)(1918)
- La Filadora(糸を紡ぐ娘)(1918)
- La Pastoreta(羊飼いの娘)(c.1918)
- La Preçó de Lleida(レリダの囚人)(c.1920)
- El Noi de la Mare(聖母の御子)(年代記載なし)
曲順については、ほぼ作曲年代順になっていることが分かる。同じ年の中での順序や、年がはっきりしているものと曖昧なもの(1900とc.1900など)の扱いについては説明されていない。
現代ギター版
2010年の現代ギター版(『ミゲル・リョベート ギター作品集~オリジナル作品と編曲作品~』現代ギター社)も、Chanterelle版(1989)と同じ13曲を収めている。

曲集全体はオリジナル曲3曲に続いて《カタルーニャ民謡集》、そのあとにファリャ、グラナドス、アルベニスの編曲が6曲という構成。加えて巻末には濱田滋郎先生による論考「カタルーニャ民謡集の元歌」が収められている。これが貴重だ。
《カタルーニャ民謡集》の内容は次の通り。
- El Testament d’Amelia(アメリアの遺言)
- Canço de Lladre(盗賊の歌)
- Lo Fill del Rei(王子)
- Plany(哀歌)
- La Filadora(糸を紡ぐ娘)
- Lo Rossinyol(うぐいす)
- El Mestre(先生)
- L’Hereu Riera(あととりのリエラ)
- La Nit de Nadal(凍った12月)
- La Filla del Marxant(商人の娘)
- La Pastoreta(羊飼いの娘)
- La Preçó de Lleida(レリダの囚人)
- El Noi de la Mare(聖母の御子)
曲順の根拠は示されていない。最初の10曲は大まかにUME版の流れを踏まえつつ少し細部を入れ換えているような感じだが、その理由は読み取れない。そしてそこに、Chanterelle版で追加された3曲が同じ順に加えられている。
Guitar Herritage版
そして2021年、「批判校訂版 critical edition」を謳ったGuitar Herritage版の『ミゲル・リョベート ギター作品集(The Guitar Works of Miguel Llobet)』全15巻が現れた(主題目録のpdfも公開されている)。


出版社はドイツのMichael Macmeekenだが、ブランド名のGuitar Herritageで通っているらしい。主宰者のマクミーケン(Michael Macmeeken、1942- )はスコットランド出身、スペインやドイツでギターと音楽学を学び、ドイツ滞在中にChanterelleという出版社を立ち上げた。そう、さっき紹介したNuevo Colecciónの出版社である。マクミーケンはリョベート作品集を2回出している訳だ。 Chanterelle社は2013年にZimmermann社に吸収されたが、マクミーケン自身は2019年にGuitar Herritageを立ち上げ、リョベート、ソル、ポンセらの批判校訂版を出す。Chanterelleの作品集は他社の版権を買って集めたものだったが、今度は新たな資料調査と編集を行って学術的にしっかりした版を出そうとしたのだった。なおこのGuitar Herritageも2023年にSchott社の傘下に入っている。
Guitar Herritage版リョベート作品集の校訂はイタリアのギター奏者グロンドーナ(Stefano Grondona, 1958 – )が行っている。シエナの音楽院で学び、ジュリアン・ブリームやアンドレス・セゴビアにも師事。数々のコンクールで活躍したあと国際的に演奏活動を展開(来日も9回)、現在はヴィチェンツァの音楽院の教授を務めている。リョベートへの関心と造詣は深く、彼が組織していた合奏団「リラ・オルフェオ」を再現した「ノヴァ・リラ・オルフェオ」を創設するほどである。マクメーケンが新しい全集を出すにあたってグロンドーナを起用したのも当然だった。
Guitar Herritage版の全集は、バルセロナ音楽博物館などが所蔵する原典資料をもとにして編纂されている。1-3巻がギター独奏曲、4-8巻が独奏用編曲、9-12巻が二重奏用編曲、13・14巻はそれぞれソルおよびカルカッシの練習曲をリョベートが校訂したもの、最後の15巻には合奏団「リラ・オルフェオ」のレパートリーが収録されている。「リラ・オルフェオ」の基本的な編成はマンドリン2部、ラウード(リュート)2部、ギター2部のようで、日本のマンドリン・オーケストラのようなものだったと思われる。
こうした全15巻の第1巻、ギター独奏曲の最初に置かれているのが《カタロニア民謡集》である。


目次に挙がっているのは22曲。といっても、《カタロニア民謡集》のもとに13曲、残る9曲は付録(Appendix)扱いである。日本語タイトルが現代ギター版にあるものはそれを、ないものは吉成の試訳([ ]で示す)を添える。
カタロニア民謡集 CANÇONS POPULARS CATALANES
- Plany (哀歌、1899)
- La filla del marxant (商人の娘、1899)
- La filadora (糸を紡ぐ娘、1st version、 1899)
- Lo rossinyol (うぐいす、1900)
- L’hereu Riera (あととりのリエラ、1900)
- Lo fill del rey (王子、1900)
- El testament de n’Amèlia (アメリアの遺言、1900)
- La pastoreta (羊飼いの娘、1st version, April 1905)
- La pastoreta (羊飼いの娘、2nd version, August 1905)
- El mestre (先生、1910)
- La nit de Nadal (凍った12月、1918)
- La filadora (糸を紡ぐ娘、2nd version, 1918)
- Cansó del lladre (盗賊の歌、1927)
付録
- La presó de Lleida(レリダの囚人)
- El Noy de la Mare(聖母の御子)
- La venjansa ([復讐]、c.1895)
- La filla del marxant (商人の娘、1900)
- L’Anunciació([告知]、1900)
- L’Hostal de la Peyra ([ペイラの宿]、1900)
- Lo rossinyol (うぐいす、c.1900, incomplete)
- M.Llobet Cançó catalana, op.4 ([カタロニアの歌]、c.1896)
- A. VIVES L’Emigrant [移民]
《カタロニア民謡集》が13曲だから全曲録音やChanterelleと同じかと予想されるが、そうではない。3と12(〈糸を紡ぐ娘〉)、8と9(〈羊飼いの娘〉)は、同じ作品の別ヴァージョンである。
ちなみに〈糸を紡ぐ娘〉の初稿(1899)と第2稿(1918)の主な違いは、後者の方が旋律の繰り返しを増やして長くなり、そのさい旋律の声部や伴奏の動きを変えて色彩感豊かになっていることであり、〈羊飼いの娘〉の初稿(1905年4月)と第2稿(1905年8月)の主な違いは、バス声部の動きを8分音符から4分音符に変えて重みを増やしていることくらいである。
つまり本編の《カタロニア民謡集》に含まれるのは作品数としては11、UME版の10曲に〈羊飼いの娘〉が加わった形。そのうち2曲の異稿を含めた11曲13稿が年代順に配置されている。
付録に目を転じると、そこにある9曲のうち6曲は実はギター独奏曲ではない。16と21はピアノ伴奏つき歌曲。17-20は「リラ・オルフェオ」のための合奏曲で、この巻では冒頭部分だけが記され、本来の楽譜は第15巻に収められている。それらがなぜ第1巻に含められているかといえば、広い意味での「カタロニア民謡集」に含まれるからである。これらを収めてくれたことによって、リョベートにとって大切な「カタロニアの人たちの歌」に関わる仕事の全体像をこの1巻で見通すことができる。
21と22は、本来の意味での民謡ではない。ふつう民謡といえば作者が意識されないものだが、この2曲は目次の表記にも作曲者が明記されている。
21はリョベート自身の作品で、カタロニア文芸復興運動の代表的な詩人バルダゲー(Jacint Verdaguer i Santaló、1845-1902)の詩に若きリョベートが付曲したもの。残念ながら自筆譜には詩人の名前が記されているだけで具体的にどの詩かは不明だが、旋律は民謡風のシンプルで味わい深い。「カタロニア民謡集」につながる仕事の最初のものとして貴重なものだ。
22はリョベートの先輩作曲家ビベス(Amadeu Vives i Roig、1871-1932)の作品で、原曲はやはりバルダゲーの詩により男声合唱団のために作曲された。故郷カタロニアを思う移民の気持ちを切々と綴る歌はカタロニアの国民歌といえるほど広まっており(カレラスもよく歌っていたようだ)、それを編曲する行為も精神的には「民謡編曲」の一環といえる。ギター独奏用だが、リョベート自身の手稿譜は残っておらず、弟子のプラット(Domingo Prat 、1886-1944)の残した手稿譜から再現されている。
ということで、付録のうち本来の意味での民謡のギター独奏用編曲は14と15、〈レリダの囚人〉と〈聖母の御子〉2曲ということになる。なぜこの2曲はここで付録扱いなのか。これについてグロンドーナは
- 自筆譜が見つかっていない。
- リョベート作と言われるようになったのはここ20年くらいのことである。
- リョベートの他の編曲作品と比べスタイルやオリジナリティの点で明らかに初歩的である。
- リョベート自身の演奏会で一度も演奏されていない。
といった理由を挙げている(Guitar Herritage版第1巻 p.44)。真作を保証する積極的な証拠が見つかるまでは、ひとまず付録扱いとする、ということだろう。妥当な判断だと思われる。
本編13曲の並びは、成立年代順である。〈糸を紡ぐ娘〉の初稿と第2稿が離れているのも、そのためだ。Chanterelle版も年代順だったが、ぱっと見にはかなり違う。理由はひとえに原典資料(自筆譜)を参照したかどうかだろう。Guitar Herritage版には〈盗賊の歌〉と〈哀歌〉の自筆譜(どちらも個人蔵)が掲載されているが、どちらも最後にリョベートの署名と日付が書かれている。ほかの曲でも同様なのだろう、本編の印刷譜にも署名と日付は添えられており、曲によって年だけ、月だけ、日までと差はあるが、Chanterelle版制作時よりかなり作曲年代が細かく分かるようになったことが掲載順に影響したに違いない。
今のところこのGuitar Herritage版が最も信頼度の高いエディションであることは確かだろう。ただ一つだけ惜しいところを指摘しておくと、この版は「批判校訂版 critical edition」と言いながら、それに不可欠な「校訂報告 critical commentary, Kritischer Bericht」がない。原典資料(自筆譜、筆写譜、初版など)の状況やその比較、異同がある場合にはその説明と判断、などを記述したドキュメントが掲載されていないのだ。資料に関する情報は序文や年譜などの中に散見されるが、網羅的・体系的ではない。校訂報告は、ただ学を衒って情報を羅列しているわけではない。資料状況をきちんと報告し、それをもとに使用者(演奏家)が自ら判断できるように(それによって校訂者と異なる結果も出せるように)、必要な情報を提示しているのだ。それが不充分なこの版は、残念ながら本来の「批判校訂版=原典版」ではなく、「原典版の要素を持った実用版」と見なさざるを得ない。もっとも、実用版の面を備えたことで、序文の中に原曲である民謡の解説が含まれていたり、巻末にはリョベートのポルタメントについての(おそらくグロンドーナによる)論考や詳細な年譜が付いていたりするのはありがたいのだが。
曲数についてのまとめ
リョベートのギター独奏用《カタロニア民謡集》に含まれる曲は何曲か。
現実的な理解としては13曲で良いのではないかと思う。
今のところ厳密には11曲なのだろう。Guitar Herritage版の本編に含まれる11曲である。上述の通りGuitar Herritage版では〈糸を紡ぐ娘〉と〈羊飼いの娘〉の異稿を含めて13と数えているが、異稿は曲として同じと考えると、曲数は11となる。
だがやはり、〈レリダの囚人〉と〈聖母の御子〉を含めた13曲とするのが現実的だ。この2曲をGuitar Herritage版が本編から外した理由については先述したが、要するにこれらをリョベートの真作と確証する根拠がない、ということである。だが自筆譜が今後発見される可能性はゼロではない。リョベートと結び付けられるようになったのが近年だというが、なぜどういう経緯でそうなったのかを探る必要があるのではないか。しかもこの版には校訂報告がないため、この2曲に関しても筆写譜や初版といった資料の情報は提示されていない。その状況で、リョベートと結びついたのが近年だからといって否定できるものではないだろう。様式的に平易だというが、例えばリョベートが初心者向けの民謡集を作ろうとしたという可能性だって考えられる。初心者向けの編曲なら、リョベート自身が演奏会で取り上げなくても不思議ではないだろう。こう考えると、この「伝リョベート」の2曲を排除する必要はまだないように思う。この2曲が新作である余地が残っている以上、当面はまだそれを含めて「リョベートの《カタロニア民謡集》は13曲」として良いだろう、と個人的には思う。
〈エル・ポブレ・パジェス〉をめぐって
冒頭にあげた昔の原稿で「その他 〈聖母とその御子〉や〈エル・ポブレ・パジェス〉等の曲が知られている」と書いた。だが〈エル・ポブレ・パジェス〉という曲は、これまで見たどのエディションにも含まれていなかった。
結論からいうと〈エル・ポブレ・パジェス〉は〈糸を紡ぐ女〉の別名で、そのことは現代ギター版掲載の濱田先生の「カタルーニャ民謡集の元歌」に書いてあった。だが当初私はそれに気付かず、〈エル・ポブレ・パジェス〉の謎を解こうとけっこう足掻いた。だが、そのおかげでこの曲を取り巻く文化を知ることができたし、ディスクや配信音源の曲目表記の混乱に気付くこともできた。以下はその顛末である。
その昔原稿に書いたということは、当時それをリョベートの民謡編曲として記載した資料を見たということだ。イエペスのレコードだったような気がする。
「リョベート エル・ポブレ・パジェス」で検索してみると、やはりイエペスのディスクがヒットした。中古CDの販売で、そのジャケットには
エル・ポブレ・パジェス(哀れな小姓)(リョベート)… EL POBRE PAGES CANCION CATALANA
と書いてある。

ここには日本語タイトルが付いているが、私が昔見たものはカタカナだけだったと思う。だから原稿にもカタカナで載せたのだ。ともあれ、ジャケットだけでは実際の音はわからないから、原題のEL POBRE PAGESで検索してみる。YouTubeのイエペスの演奏が3つある。いずれも表示されているジャケット写真が違うから3種類のディスクのようだが、聴いてびっくり。なんと3つとも〈盗賊の歌〉だ。タイトルの表記はEl Pobre PagesとEl pobre pagésがあるものの、演奏はそっくりで音源は同じようだから、おそらく原盤の段階でEl Pobre PagesなりEl pobre pagésとクレジットされていたのだろう。それにしてもなぜ〈盗賊の歌〉が別の名で呼ばれているのか。
検索ページにはイエペス以外のYouTube動画も2つ見える。Cobla Ciutat de Bergaという演奏者のをクリックしてみる。
これまたびっくり、〈糸を紡ぐ女〉を吹奏楽で演奏している。カタロニアの都市ベルガの市民バンドのようだ。ちなみにもう一つのMúsica de la Patumという動画も同じ演奏だった。Patumというのはベルガ市のお祭りで、「神秘的で象徴的な人物に扮した町民による一連の「踊り」で構成され、太鼓(その音が祭りの名前の由来となっているタバル)のリズムまたはバンド音楽が伴奏されます。」(Wikipedia英語版の自動翻訳)ということだ。その様子を撮影した動画もある。
動画のタイトルにはっきりEl Pobre Pagésと書いてあるから、この人たちにとってこの曲は間違いなく〈エル・ポブレ・パジェス〉であって〈糸を紡ぐ女〉ではないのだろう。 〈エル・ポブレ・パジェス〉は〈盗賊の歌〉なのか〈糸を紡ぐ女〉なのか。
ところでEl Pobre Pagésをアクセント記号の付いた形でグーグル翻訳に放り込むと、「貧しい農民」と返ってくる。上記の中古CDで「小姓」と訳していたのは英語からの連想で納得できたが、「農民」という意味もあるらしい。
ちなみにイエペスの録音で「貧しい農夫」という日本語タイトルの付いているものがYouTubeにあった。これも原題はEl Pobre Pagésではないかと思って、聴いてみたら、〈糸を紡ぐ女〉、それも初稿の方だった(細部に若干の違いはある)。
ちなみに〈糸を紡ぐ女〉の初稿は、これまで見てきたエディションの中では2021年のGuitar Herritage版で初めて登場するが、実はその100年前、ロシュ(Pascual Roch、1864-1921)の『現代ギター教本(Método moderno para guitarra)』(1921)の中で出版されていた。リョベート編曲ともきちんと書いてある。イエペスが弾いているのはおそらくこれに違いない。

この動画には音源の出典が書いてないので原題が確認できない。「イエペス 貧しい農夫」で検索したら、『入り江のざわめき〈イエペス名演集〉』(KING KICC2219)というCDがヒットした。スペインZAFIRO社の原盤らしい。


ケース裏のトラック一覧を見ると
[4] リョベート:貧しい農夫 LLOBET: EL POBRE PAGES – Cancion Catalaña
とあって
[5] リョベート:盗賊の歌 LLOBET: CANCO DEL LLADRE – Cancion Catalaña
と並んでいる。
El Pobre Pagesと Canço del Lladreが並んでいるグラモフォン以外のディスクを探してみたら、各種ストリーミングサイトに挙がっている”Masters of the Spanish Guitar: Narciso Yepes – The Second Recital”(Jube Classic)というアルバムがあった。

トラック9にCanço del Lladre、トラック10にEl Pobre Pagesがある。聴いてみると、またまたびっくり。トラック9が〈糸を紡ぐ娘=El Pobre Pages〉の初稿でトラック10が〈盗賊の唄〉だ。タイトルと音源が入れ違っている。Naxos Music Library(NML)でもSpotifyでも同じだから、Jube Classicの元データが間違ってるのだろう。
配信データの間違いついでに書いておくと、NMLでCanciones populares catalanas: El mestre (The Teacher)つまり〈先生〉として挙げられているデータ(アルバムは日本では「バッハ/ファリャ/タレガ/トゥリーナ/ヴィラ・ロボス:ギター作品集(イエペス)」原タイトルは”Nächte in spanischen Garten” 、Grammophon)は、聴いてみると〈先生〉のあとに〈盗賊の唄〉が続いている。1つのトラックに2曲入っているのに、最初の曲のタイトルしか示されていない。同じものをSpotifyで確認すると、そのトラックのタイトルはDos Canciones Populares Catalanes(2つのカタロニア民謡)となっている。個々の曲名はないが、ちゃんと2曲と書いてある。おそらくNMLの日本スタッフが気をきかせて曲名を添えたつもりが2曲目の存在に気付かなかったのではないかと想像される。
NMLでもう一つ。実はここにGuitar Herritage版の校訂者グロンドーナが録音したリョベート作品集がある。本来はstradivariusレーベルのCD2枚組で、Disc1にリョベートのオリジナルとアルゼンチン民謡の編曲、Disc2に《カタロニア民謡集》が収められている。録音は2003年から2006年にかけて行われており、Guitar Herritage版以前に知られていなかった曲は入っていない。《カタロニア民謡集》も、Chanterelle版や現代ギター版と同じ13曲だ。演奏はとても良い。ところが、《カタロニア民謡集》のうち3曲が表記された曲名と実際の音が違っている。トラック8のLa Nit de Nadal(凍った12月)は実際はLa Filla del Marxant(商人の娘)だし、トラック9のLa filadora (糸を紡ぐ娘)は実はLa Nit de Nadal(凍った12月)、トラック10のLa Filla del Marxant(商人の娘)が実はLa filadora (糸を紡ぐ娘)。困ったことにこの間違いはNMLのミスではない。実はもとのCDからトラック表記と実際の曲が違っているのだ。なぜ、よりによってグロンドーナのCDでこんなことが起こっているのか。グロンドーナ本人が気付かないはずはないだろうに。このCDの演奏はYouTubeにも上がっているのだが、当然のようにそこでもこの間違いは引き継がれている。本当にもったいない。
と、ここまで四苦八苦しているうちに、どうやら〈エル・ポブレ・パジェス=貧しい農夫〉と〈糸を紡ぐ娘〉は同じ曲である可能性が高そうだと思うようになり、ひょっとして「貧しい農夫」の娘が「糸を紡ぐ娘」なんじゃないか、と思い至って、歌詞を確認しようと濱田先生の「元歌」を開いたら、何のことはない、「糸を紡ぐ娘 LA FILADORA または 貧しい農夫 EL POBRE PAGÉS」と書いてあったのだった。
未解決なのは、イエペスの弾いた〈盗賊の唄〉が外国でも日本でも昔から〈エル・ポブレ・パジェス〉として通ってきた謎だ。カタロニアやスペインの人たち、日本のギター関係者たちは気付かなかったのだろうか。
〈糸を紡ぐ女〉が〈貧しい農夫〉でもあるように、同じ曲が複数のタイトルを持つことはある。同じメロディーに複数の歌詞が付くこと、つまり「替え歌」は古今東西よくあることだが、イギリスのバラッドなどでは同じ歌詞に複数のメロディーが付くこともある(別項参照)。可塑性の高いのが民謡というものだ。だが、〈盗賊の唄〉が〈エル・ポブレ・パジェス〉として通用している例は、イエペスの古い録音以外に見つからない。単なる「ミス」でもなさそうな、何か背景があるような気がしている。
ともあれ、ディスクや配信のデータがこんなに混乱しているのは、本当に困ったことだ。リョベートだけでこれだけの混乱が生じているのだから、ほかの作曲家たちの作品でも同じことは起こっているのだろう。知らない曲をネットで探して聴くときは気を付けよう。
曲順について
さて、楽譜や音源で《カタロニア民謡集》全曲を収録する場合の曲順について考えてみる。各曲を個別に取り上げたり何曲か抜粋するような場合は曲順を考える必要はない。だがとくに曲集として出版する場合には、曲順に対する配慮があっても良いのではないだろうか。
次の表は、本稿で先に取り上げたエディションの曲順である。

まず1933年にUME版の10曲集が出た。おそらくそれをもとに1964年にギタルラ社版が出る。その後全集を意図して1989年にChanterelleが13曲のまとまりを出版。2010年に出た現代ギター社版は、Chanterelle版の13曲を含んでいるが、曲の配置ではややUME版の影響が感じられる。そして2021年にChanterelleより完成度の高い全集としてCuitar Herritage版が出る。本編に含まれるのは11曲13稿、付録扱いの2曲を加えてChanterelle版と同じ13曲になる。Chanterelle版とGuitar Herritage版の曲順は成立年代順だった(出版当時の資料状況によって両者の違いが生じている)。
ここで考えたいのはUME版の年代である。最初の版権表示は1933年。リョベートの生前である。当然その出版には作曲者本人が関わっていたはずであり、その曲順にもリョベートの意思が反映したと考えるのが当然だろう。もちろんこの《民謡集》は組曲として作られた訳ではなく各曲の独立性は高いのだが、だがこの10曲は一つの曲集としての「まとまり」を持っている。少なくともリョベートは、その「まとまり」を意識していたはずだ。なぜなら、UME版が出版された時点でリョベートのカタロニア民謡編曲はこの10曲だけではなかったからだ。
真作かどうかが問われている〈レリダの囚人〉と〈聖母の御子〉を除いても、確実に〈羊飼いの娘〉はあった。リョベート本人がその存在を忘れていたとか、入れたかったけど自筆譜が見つからなかったとか、そういう可能性も理屈ではありうるが、考えにくい。Guitar Herritage版が明らかにしたように〈羊飼いの娘〉には2つの稿が残っている。一度編曲し数か月後にまた手を加えるだけのこだわりを持っていた〈羊飼いの娘〉をリョベートが忘れるはずがないし、初稿も改訂稿も楽譜が手元にない、ということも考えにくい。ではなぜ〈羊飼いの娘〉はUME版に含まれなかったのか。
何か、外さざるを得ない事情があったのだろう、と私は思う。出版上の制約――たとえば出版社が切りの良い10曲でまとめてくれと頼み、やむをえず外した――とか、音楽的なバランス――ほかの曲と比べて素朴で軽すぎる――とか。このあたり、Guitar Herritage版が本当の意味で批判校訂版であれば必要なドキュメントも提示してくれた可能性はあるが、残念ながらそうではないので、こちらはひたすら妄想を巡らせるしかない。リョベートの意思によるものか、不本意ながら引き受けざるを得なかったのかは分からないが、とにかく何らかの事情で外すことになった。
そうして選んだ10曲を、適当に、なんに配慮もせずに並べるだろうか。当然、曲集としてなるべく効果的になるよう配列を工夫したはずだ。技術的な難易度とか、曲の雰囲気とか、知名度とか。配列の理由をくみ取れるほどの知識が私にはないので分からないが、20年以上の長い間少しずつ書き貯めてきた民謡編曲を世に出すのだから、それなりの意を尽くした形に仕上げたはずではないか。だから、《10のカタロニア民謡》というタイトルとその曲順は、そこに曲を追加したとしても、尊重すべきだと私は思う。例えば以下のように。
10のカタロニア民謡(リョベート作曲)
- 第1曲 アメリアの遺言
- 第2曲 盗賊の歌
- 第3曲 糸を紡ぐ女
- 第4曲 王子
- 第5曲 うぐいす
- 第6曲 哀歌
- 第7曲 先生
- 第8曲 あととりのリエラ
- 第9曲 商人の娘
- 第10曲 凍った12月
カタロニア民謡(リョベート編曲)
- 羊飼いの娘
- レリダの囚人
- 聖母の御子
演奏の場合も、全曲通して演奏する場合は同様の並べ方が良いと思うのだが、どうだろうか。演奏会などではプログラム全体の構成なども考慮して演奏効果の望ましい配列を考えてもよいと思うが、全曲録音盤などの場合は半ば作品目録的な性格も帯びるので、10曲のまとまりは考慮すべきだと思う。
参考までにNMLに挙がっている《民謡集》全曲録音の曲順を調べてみた。グロンドーナには2000年と2007年の2つがあり、新盤については先述の通り表記と実際の音が違っているので、両方の曲順を並べている。

一つとして同じものがないのは面白いが、聴き手は混乱しないだろうか。
日本語タイトルについて
これまで本稿では、ギタルラ社版の紹介時以外、日本語タイトルはギタルラ社版のものを示してきた。現在一般的になっている全13曲を収めた日本の楽譜として、今後も標準的な位置を占めると思われるからである。これまでにも日本語タイトルの混乱はあったし、現代ギター版のものにもやや疑問点はある。そこで日本語タイトルについて考えてみる。
原題と現代ギター版の日本語タイトル、ギタルラ社の日本語タイトルを並べてみた。その他ネットなどで確認できたものも添えてある。曲順は、前項で示したUME版+3曲の順である。

〈アメリアの遺言〉 「遺言」と「誓い」はtestamentの訳し方。とある城の姫が今わの際に語るのだから、「遺言」で良いだろう。
〈盗賊の歌〉 「歌」と「唄」は、まあ、訳された時代の違いだから、今なら「歌」でよいだろう。「盗賊」については、ある動画では「義賊」のような存在として説明されているが、歌詞を見る限り、もっと単純な悪党だろう(「お金の次は女」というのは義賊のセリフではない)。
〈糸を紡ぐ女〉 「紡ぎ女」はちょっと古い感じ。今の人には意味が分かりにくいだろうし、コンプラ的にも抵抗がありそう。「エル・ポブレ・パジェス」は上述の通り〈糸を紡ぐ女〉の別名。
〈王子〉 これについて揺れはないようだが、原題が “príncep” ではなくわざわざ “Lo fill del rey” となっているのだから〈王の息子〉でも良さそうに思うのだが。
〈うぐいす〉 原題の rossinyol は日本の「鶯」とは違う。英語のナイチンゲール、日本の詩などでは昔から小夜鳴鳥と訳されてきた。ロマンチックな呼び名だと思うのだが、古いだろう。そこで「夜うぐいす」「夜鳴きうぐいす」いっそ言語に近く「ロシニョール」「ナイチンゲール」、ということになる。いずれにしても「うぐいす」は誤解を招くと思う。「夜うぐいす」があっさりしてて良いかな。
〈哀歌〉 出版譜に揺れはないのだが、ディスクなどでは原語のカタカナ表記もあるようだ。「プラニー」では分からないだろう。「プラニー(哀歌)」のような表記もあるようだが、それならいっそ「哀歌」で良いのではないか。濱田先生が「悲憤に満ちた愛国歌」と仰るとおり他国によるカタロニア支配を憤る歌であって、単なる「悲しい歌」ではないということを示したいのかもしれないが。
〈先生〉 ギタルラ社の「教師の恋」は歌詞の内容の反映か。「教師」だと恋の歌だと分からない、と気をきかせたのかもしれないが、これでは教師の心情を歌ってるみたい。教師に惚れられたのに戦争に取られてしまった娘の心配と悲しみだと分からない。〈エル・メストレ〉では意味が分からないうえに「親方」かもしれず、歌詞に合わない。
〈あととりのリエラ〉 hereu は「相続人」。ギタルラ社の「将軍」は何か別の単語と勘違いしたのだろう。「あととりの」で良いのだが、昔ON BOOKS(冒頭の引用文)で「あとつぎの」と訳したのは、「あととりの」という平仮名の並びが一瞬意味を取りにくそうに思ったからだったような気がする。
〈商人の娘〉は、問題なし。訳の揺れもない。分別を知らずに育った娘の過ち。濱田先生の説明には歌詞より先の内容まで書かれているので、本来の詩はもっと長いのかもしれない。
〈凍った12月〉 UME版とChanterelle版の(目次ではなく)楽譜上部に書かれたタイトルには”LA NIT DE NADAL (EL DESEMBRE CONGELAT)”とある。一方Guitar Herritage版と現代ギター版はともに”LA NIT DE NADAL”のみ。”La nit de Nadal”は「クリスマスの夜」、”El Desembre congelant”は「凍てつく12月」。だから、UME版のタイトルを「聖夜(凍れる12月)」と訳したギタルラ社版はとても正しい。「クリスマスの夜」は英語(christmas night)でもクリスマス前夜、クリスマス・イヴのことだから、「聖夜」という訳も良い。一方、原題としてLa Nit de Nadalだけ挙げながらそこに「凍った12月」という日本語タイトルだけ示す現代ギター版はおかしい。そもそも「凍った12月」だけではクリスマスの歌だということも伝わらない。濱田先生の「元歌」での題は「凍った12月 LO DESEMBRE CONGELAT または クリスマスの歌 CANSO DE NADAL」となっている。この解説を読まずにギタルラ社版の目次と楽譜だけ見た人には何の歌だか分からないだろう。これは明らかな編集上の手落ちというべきだ。
〈羊飼いの娘〉も問題なく、訳の揺れもない。強いていうなら「羊飼いである娘さん」ではなく「親が羊飼いの娘さん」とも取れてしまう(「商人の娘」が「親が商人である娘」だったように)のだが、だからといって「羊飼い女」という訳にもいかず、これで良しとしよう。
〈レリダの囚人〉 原題はChanterelle版と現代ギター版で”La Preçó de Lleida”、Guitar Herritage版で”La presó de Lleida”。このタイトルと日本語タイトルを比べて真っ先に浮かぶ疑問は、なぜLleidaが「レリダ」と表記されるのか。レリダはカタロニアの地名で、スペイン語でレリダ、綴りはLérida、カタロニア語ではリェイダ、綴りはLleida。現代ギター版では原題をカタロニア語で表記しながら日本語タイトルの方はスペイン語の読み方になっている。タイトルがカタロニア語綴りなら読み方もカタロニア風のカナ表記であるべきではないのか。民謡集のまとまりに対しては目次で《カタルーニャ民謡集》とカタロニア風発音に従っているのだから、この曲も〈リェイダの囚人〉とすればよかったのだ。
「それならこのブログでもカタロニアではなくカタルーニャと表記しろ」「リョベートじゃなくてリョベットだ」などという声が聞こえてきそうだが、当ブログでは「日本で一般に親しまれている表記に従う」ことを方針としているので、今のところはカタロニア、リョベートで通させてもらう。問題にしているのは現代ギター版の原題表記と日本語タイトル表記のずれである。リョベートの原題がカタロニア表記なのだから、読み方もカタロニア風にして「La presó de Lleida リェイダの囚人」ではないか。
――と、現代ギター版にならってpresóあるいはpreçóを「囚人」と訳してきたが、上記の表のようにこれを「監獄」と訳している例もある。グロンドーナ旧盤のNMLである。原曲の歌詞は「レリダの街に牢屋があって」と始まり、その囚人の一人にお姫様が恋をする、という話なのだから、タイトルとしては「牢屋」「監獄」の方がふさわしい気がする。ちなみにスペイン語のGoogle翻訳にpresóと放り込むと「囚人」と出る。同じ単語を本来のカタロニア語として放り込むと「刑務所」と出る。やはり〈リェイダの監獄〉が良いように思う。
〈聖母の御子〉 これも訳に揺れはない。カタロニアの伝統的なクリスマスソングであり、セゴビア編曲でも知られ、日本語タイトルも定着している。だが原題は”El Noi de la Mare”、 「母の坊や」。歌詞にも宗教的な言葉はない。カタロニア語などのWikipediaにあるように、もともと普通の童謡だったものがクリスマスでも歌われるようになり、クリスマスソングの定番になっていったようだ。やさしい子守歌。〈お母さんの坊や〉くらいで良いような気もするが。
以上、リョベートの《カタロニア民謡集》の曲数とエディション、曲の順序と日本語タイトルについて、門外漢ながらいろいろ調べ、考えてみた。思いのほか手こずったが、現状の把握と問題点は理解できたと思う。
最後の口直しにグロンドーナの演奏動画をどうぞ。2006年、バルセロナでの演奏会。ちょうど2度目の《民謡集》全曲録音と同じ頃だ。〈凍った12月〉〈アメリアの遺言〉〈聖母の御子〉〈哀歌〉〈王子〉〈羊飼いの娘〉の6曲を弾いている。
![musiquest [音楽探求]おぼえがき](https://musiquest.sakura.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2024/11/wpロゴ2色小文字.jpg)